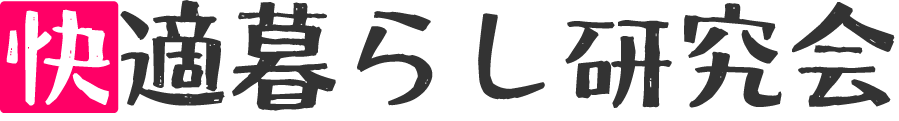20年ぶりにミルクパンを新調した。
2025年の夏、私は濃厚なミルクティー作りに凝っていた。牛乳に紅茶の茶葉を直接入れ、コトコトと煮出す。火加減はごく弱火。沸騰させてはならない。表面からふわっと湯気が立つ60〜70℃を保つのが理想だ。
だが、独身時代から20年近く使ってきた安物のミルクパンには、繊細な作業に限界があった。鍋の厚みが薄いため、火加減を間違えると噴火するように吹きこぼれ、すぐに底が焦げ付く。
そこで、新しい鍋を迎えることにした。
我が家にはすでにZWILLING(ツヴィリング)社の別の鍋があり、その美しさと堅牢さを信頼していた。購入したのは同社の「ピコ ミルクポット 14cm 1.5L」。価格は4,000円台。

手にした瞬間、ずっしりとした重みと、磨き上げられたステンレスのフォルムに惚れ惚れした。ガス火、IH、オーブンすべてに対応する分厚い底。まさに完璧な鍋を手に入れたと満足していた。
しかし、3か月使って気づいた。
私は「ミルクパン」を買ったつもりだったが、これは「ミルクポット」だった。
その違いは、日常使いでの戸惑いとして現れた。まず、鍋の内側に目盛りがない。ミルクティーやココアのために牛乳を温めようにも、分量がいまひとつ分かりにくい。
次に、注ぎ口(くちばし)がない。
「ミルクパン」なら当然あるはずの注ぎ口がない。丸いフチからカップにそそぐと、液体はやや不安定に揺れ、鍋の側面を牛乳が伝っていく。
そして、付属のフタがない。私は「完璧なものはこの世には存在しない」と、ふと思わされた。
だが、この不完全さこそが「ポット」の証だった。「パン(Pan)」が調理(温め・注ぎ)に特化しているのに対し、「ポット(Pot)」は深い容器や多用途の鍋を指す。
これはミルクティー「専用」ではなく、みそ汁やスープも作り、オーブンにも入れられる「汎用」の小型鍋だったのだ。コンロの奥にある小さな「バックバーナー」も有効利用できる。
「汎用性」ゆえの「不完全さ」が、あの古いミルクパンに新しい役割を与えた。独身時代に買った安物のミルクパンは、計量係としていまだ健在。都合よく、内側に目盛りが付いている。

不完全さを受け入れ、互いに補い合いながら存在する―わが家の台所。